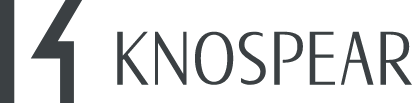2025.08.01
「TG-WEB」とは
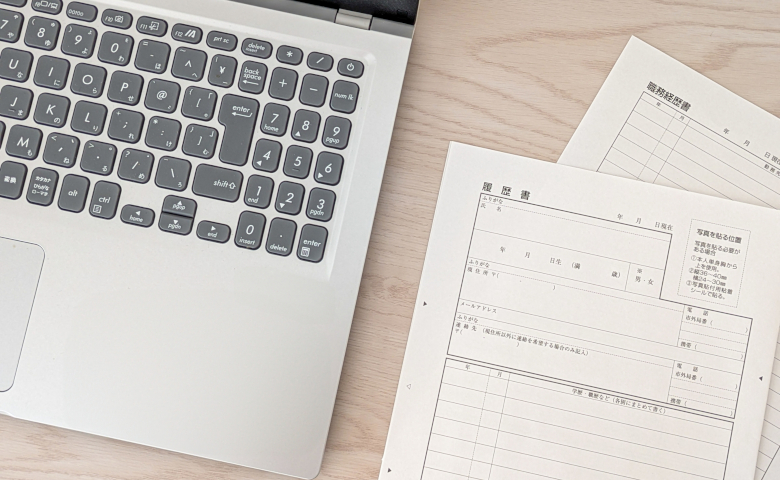
今回取り上げるキーワードは「TG-WEB」。
概要としては、SPIと同じく、主に就職活動の選考に用いる適性検査の一種で、株式会社ヒューマネージが提供するサービスです。
同社が公表したプレスリリースによると、TG-WEBの提供開始は2000年で、今年25周年。
しかし、適性検査のシェアは長らく、圧倒的にSPIが占めており、それに玉手箱、CAB/GABなどが続いている状況でした。 ところが、ここ数年で急激に、講座でTG-WEB対策を求める声が大きくなりました。
その声に応えるべく、その背景と対策を調べ、自社サービスに活かすようナスピアの視点でまとめてみました。
まず、TG-WEBがシェアを伸ばした背景について。
いくつも要因が考えられますが、まずはコロナ禍における非対面式の需要に合致したことが挙げられます。2020年には、無料で企業にTG-WEBを提供する試み(数量限定)を行うなど、時勢を味方につけ、シェアを伸ばしたと考えられます。
次に、非対面式Webテストで対策が難しい不正防止にも注力していること。AI監視による不正防止を試み、企業側に安心材料を与えています。
最後に、他サービスとの差別化。一般的にTG-WEBは難易度が高いと言われますが、それ以外にも自由に組み合わせできる検査ラインナップ、多角的な分析という強みをアピールし、新入社員の選考以外の場面でも使用できるサービスとして、差別化を図っています。
上記で触れた通り、「TG-WEBは他のサービスに比べて難易度が高い」と言われますが、これは「従来型」と呼ばれるものです。設問の難易度が高い上に、数が少なく、他のサービスよりも強力に「ふるい落とし」を行う、そんな一面があります。
それが求められたということは、逆にいえば「SPI」では十分な「ふるい落とし」ができない悩み・ニーズがあった、と考えられます。
それは、高偏差値の大学から応募者が殺到するような企業なのかもしれませんし、SPI対策が広く知れ渡った結果かもしれません。ともかく、そうしたニーズに、TG-WEBの戦略はぴったりと合致したのでしょう。
さて、「従来型」があるのですから当然「新型」も存在します。
これは「従来型」に比べ難易度が低く、設問数が多くなっている…つまり、SPIと同じターゲット層まで手を広げたということです。
あくまで「従来型」の好調と、「独自の強み」ありきでしょうが、勇気あるマーケティング戦略に思います。
では、結局受検者側は、どのようにTG-WEBに対策すればいいのでしょうか?
実は、 TG-WEB の設問ジャンルには、SPIと共通しているものも多く見られます。
- 計数(=SPIでいう非言語能力):推論や図形(展開図/空間図形)、図表、四則逆算など
- 言語(=SPIでいう言語能力):同義語・対義語・四字熟語やことわざ、文脈理解・語彙力、中~長文の要旨・解釈など
これらは、弊社のSPI.StudyCampで既にドリルや解説動画でサポートしており、制限時間がある中で、実践さながらの練習が可能です。
一方で、独自色の強い出題ジャンルも存在しており、これらについては2026年春までに対策問題を導入すべく、準備を進めています。
- 計数(=SPIでいう非言語能力):図形(一筆書き/ジグソーパズル/折り紙)など
- 言語(=SPIでいう言語能力):高難度の長文読解(要旨・解釈)など
- 英語(オプション):高難度の長文読解(要旨・解釈)や言い換えなど
例えとして書きましたが、SPI対策が広く知れ渡った結果、十分な「ふるい落とし」ができなくなった、というのは何も冗談ではありません。
選考対策の重要性は各所で強く説かれており、『対策をしていない』というだけで大きく出遅れてしまう時代なのです。
時勢に合わせ教材研究を怠らず、ナスピアではサービスのブラッシュアップを続けてまいります。
Written by Y.Nakai
本番で実力通りの力を発揮する出題形式を搭載
ナスピアの提案するSPI対策e-learningはコチラ![]()