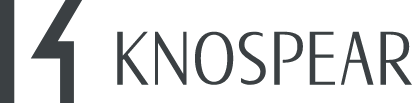2025.10.01
読解力を鍛えるには?

今回のキーワードは「読解力」。
読解力とは、文章を読んで内容を理解し、解釈する力のこと。勉強や仕事だけでなく、相手の意図を正しく把握し円滑なコミュニケーションを図る、情報過多な現代において必要な情報を読み取るなど、日常生活に欠かせない力と言えます。
みなさんは、読解力に自信がありますか?私は、正直もっと伸ばしたいなと思うときがあります。たとえば、主語や目的語が省略されている文章や、別の解釈ができてしまう文章に触れたときです。また、何度読んでも頭に入ってこない文章もあります。
リーディングスキルテスト(RST)を開発し、AIに関する著書でも広く知られる新井紀子氏によると、実は教科書を読み解くことにつまずく子どもが大勢いるとのこと。さらに、過半数の大人は新聞記事が読めていないというのです。
では、読解力を鍛えるにはどうすればいいでしょうか?
- 文章の構造を意識しながら読む
係り受け(主語と述語、修飾語と被修飾語など)を意識して読む、助詞や接続語に注目して読む、5W1Hを意識して読む、などです。長文読解の学習方法も参考になります。
- 論理構成を把握する
段落単位で文章全体を分析し、主張や反論、補足など、それぞれの役割を考え、何を伝えたいのかを捉えます。
- 要点をメモに取りながら読む
重要だと思うことをメモに取りながら読みます。なかなか頭に入ってこない文章は、図にするのも1つです。
- 読んだ後に要約し、アウトプットする
いきなり書籍1冊となるとハードルが高いので、目次の最小単位から始めたり、短めの新聞記事から始めたりするとよいでしょう。
アウトプットする方法の1つとして、私も最近、新井氏の著書『シン読解力』で紹介されていたトレーニングを実践し始めました。新聞から1日1記事を選び、「リード文の内容を読んで、見出しの言葉をできるだけすべて使い、1文でまとめる」というものです。
とはいえ、1人で取り組むのはなかなか難しいものです。そこで、学生であればeラーニングで手軽に取り組めるトレーニングも活用してもらえたらと思います。
BASIC.StudyCampでは、「聴く」「読む」「書く」など8つのスタディスキルを養う教材において、読解力を鍛えるための要素を盛り込んでいます。要約を考える問題や、助詞や接続語を穴埋めする問題などです。要約を考える問題では、作問技術のコラムでも触れている通り、「あながち間違いではないが、より適切なものがあるので誤り」という選択肢を混ぜ、しっかり読解しないと解けないような工夫をしています。
また、とりわけユニークな問題として、メモを取りながらニュースを聴き、聴き終わったら問題が出題されるという形式もあります。ニュースを聴いている時点では問題の内容が分からないため、要点をメモに取りながら聴くトレーニングができます。
このような様々な趣向を凝らしたトレーニングを通して、読解力を鍛えていきましょう!
Written By Y.Koyama
新聞記事を使ったeラーニングで「社会人基礎力」を養成
独自に定める『8つの力』を身につけよう